
といった悩みにお答えします。
本記事の内容
- マンションの購入でもクーリングオフは可能!
- クーリングオフできる条件は5つ
- クーリングオフ以外の解約方法は4つ
- クーリングオフの手続きと注意点
結論からお伝えすると、マンションを購入した場合でもクーリングオフは可能です。
とはいえ、「マンションを購入してクーリングオフするのに、何か条件はあるのでしょうか?」「クーリングオフする場合の手続きを知りたい!」といった悩んでいるのではないでしょうか?
今回は、マンションを購入した場合のクーリングオフについて解説していきます。
本記事を読むことで、マンションを購入した場合のクーリングオフの条件やクーリングオフのやり方について知ることができます。
ちなみに、クーリングオフができるのは売主からクーリングオフの説明を受けてから8日間と今っているので、マンションを購入して8日以内の方は要チェックです。

-

【保存版】マンション購入から引渡しまでの手順について
続きを見る
マンションの購入でもクーリングオフは可能!

冒頭でもお伝えした通り、マンションを購入した場合でも、クーリングオフすることは可能です。
では、「そもそもクーリングオフとは何か?」「クーリングオフってなぜできたの?」といった疑問から解決していきましょう。
そもそもクーリングオフとは
クーリングオフとは、物品購入の申し込みを行った場合や、すでに契約をした場合でも、一定の期間内であれば契約の撤回が可能です。
契約の解除が可能ですので契約自体を無効にすることができる制度です。
ただし、注意すべきは「全ての契約においてクーリングオフが可能というわけでない」ということです。
主なクーリングオフが可能な取引や期間を下の表にまとめました。
クーリングオフ可能な取引と期間
| クーリングオフ可能な取引 | クーリングオフ可能な期間 |
| 訪問販売(キャッチセールス等) | 8日間 |
| 電話勧誘による販売 | 8日間 |
| 連鎖販売(マルチ商法等) | 20日間 |
| エステや学習塾など継続的な取引販売 | 8日間 |
| モニター商法や内職などの勧誘 | 20日間 |
| 訪問による買取購入 | 8日間 |
上記のように、クーリングオフが可能な取引においては、クーリングオフすることで、契約を撤回することが可能です。
しかし、条件によっては上記のような取引においてもクーリングオフができない場合があります。
クーリングオフできる条件については、後述していきます。
クーリングオフ制度はなぜできたのか
クーリングオフ制度ができたのは1972年と制度ができて半世紀ほど経過します。
高額な商品を訪問販売により分割払いで購入させるといったケースが相次ぎ、消費者被害が続出したことを受け割賦販売法が改正されましたが、その際に同時に設立されたのが、クーリングオフ制度です。
クーリングオフ制度ができるまでは、一旦契約すると契約の撤回がなかなかできず、契約を撤回すると多額の違約金を請求されるといったことも少なくありませんでした。
しかし、クーリングオフ制度の設立により、今までは泣き寝入りしているようなケースでも堂々と契約の撤回をできるようになり、消費者保護に一役買うことになりました。
ちなみに、特定商取引法の条文自体には「クーリングオフ」という文言はありませんが、各取引において「契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付」の中で、申し込みの撤回(クーリングオフ)についての内容が記載されています。
マンションの購入でクーリングオフできる5つの条件

マンションの購入でクーリングオフしたい場合には、以下の5つの条件が必須となります。
- 引き渡し前であること
- 売主が宅建業者であること
- 買主が宅建業者以外であること
- 制限された場所以外で申し込んでいること
- クーリングオフの説明から8日以内であること
1つずつ解説していきます。
その①:引き渡し前であること
マンションの購入は、申し込みから引き渡しまで一定の時間がかかってしまうのが一般的です。
基本的にはマンションの引き渡しと同時に代金を支払いますが、引き渡しが終わっているマンションにおいては、クーリングオフの適用対象外となります。
しかし、少ないケースですが、代金の精算が行われない状態でマンションの引き渡しが完了していることがあるのです。
逆にマンションの引き渡しが行われず、代金は支払い済みといったケースもあります。
このようなケースにおいてはクーリングオフの対象となりますので、理解しておきましょう。
その②:売り主が宅建業者であること
クーリングオフの条件として、不動産のプロである宅建業者などとの取引において不利にならないようにクーリングオフ制度を認めています。
売主が宅建業者の場合、不利な契約内容であってもうまく丸め込まれて契約されてしまう可能性が考えられるでしょう。
つまり、売主が宅建業者ではなく個人だった場合などは適用外となります。
多くの契約は、個人の売主と個人の買主の契約が多いのですが、新築マンションの場合は、宅建業者が売主となっているケースが多いです。
この場合はクーリングオフの適用となります。
マンションを購入する場合、売主は不動産業者であるかどうかを前もって確認しておくことをおすすめします。
その③:買主が宅建業者以外であること
クーリングオフ制度は、一般消費者の保護が最も大きな目的とされています。
そのため、買主が個人の場合に適用され、買主が宅建業者の場合は適用外です。
これは、ある種当然といえば当然でしょう。
お互いにプロ同士である不動産の専門家同士の取引となりますので、この場合にはクーリングオフを活用する必要性が見当たりません。
その④:制限された場所以外で申し込んでいること
マンションの購入を申し込んだ場所においても一定の制限がかかります。
ではどのような場所で申し込みを行うとクーリングオフの対象外となるのでしょうか?
クーリングオフ適用外となるのは以下の場所で申し込みを受けた場合です。
- 事務所
- 店舗
- 営業所
- 住宅展示場
これらが、クーリングオフができない申し込みの場所となります。
その他にも、買主が希望して自宅や勤務先などでの申し込みを望んだ場合でも、クーリングオフの対象外となりますので注意しておきましょう。
その⑤:クーリングオフの説明から8日以内であること
他の取引と同様にマンション購入においてもクーリングオフが適用となる期間が定められています。
マンションの購入において、売買契約や重要事項説明というのを行わなければならず、その場合にクーリングオフの説明が行われることが多いでしょう。
この場合、クーリングオフの説明を受けてから8日間以内であり、かつ前述した条件を満たしていればクーリングオフの適用範囲です。
しかし、売買契約や重要事項説明などにおいてクーリングオフの説明を受けなかったらどうなるのでしょうか?
この場合は、期間の定めは無くなり、引き渡しと代金の支払いが完了するまでクーリングオフの対象となります。
他の販売方法とは若干異なりますので違いをしっかりと把握しておきましょう。
クーリングオフ以外の4つの解約方法

続いては、クーリングオフ以外でマンションの購入を解約する方法をご紹介します。
- 売買契約前に解約
- 手付金を支払って解約
- 違約金を支払って解約
- 住宅ローンの審査が通らないから解約
1つずつ解説していきます。
その①:売買契約前に解約
基本的に、マンション購入の申し込みから売買契約に至る間に解約するのは特に違約金などを負担することなく解約が可能です。
できれば、きちんと判断したうえで、なるべく解約することなく進めていきたいのは誰もが同じ思いでしょう。
ですが、どうしてもマンション購入が負担になってしまう場合などにおいて、キャンセルすることは出てくるかもしれません。
マンション購入において、どうしても解約する場合は、売買契約前に行えば、金銭面の負担をすることなく解約することが可能です。
その②:手付金を支払って解約
売買契約を交わすときに手付金をいっしょに支払わなければいけません。
手付金には、証約手付、解約手付、違約手付などの3種類の意味合いを持つ手付金があります。
マンション購入などの不動産売買においての手付金の位置づけは解約手付としての意味合いが一般的です。
解約手付とは、売買契約締結後一定期間内であれば手付金を放棄して売買契約を解除できる意味合いの手付金であることを指します。
万が一キャンセルとなった場合には、買主は手付金を放棄して契約をキャンセルすることが可能です。
手付金放棄の期間内であれば売主も解約することができますが、この場合は手付金の2倍となる額を買主に支払わなければいけません。
手付金の放棄によるキャンセルに関しては、あらかじめ期限が定められています。
その期間内においてキャンセルする場合は、手付金相当額によるキャンセルが可能となるのです。
その③:違約金を支払って解約
手付金には有効期間があります。
この有効期間を過ぎてしまうと、手付金の放棄ではなく違約金を支払う必要があります。
手付金を納める額に関しては一般的に5%~20%の範囲内だといわれており10%前後が一般的な手付金額といったところでしょう。
しかし、違約金となってしまうと売買代金の20%程度が一般的となり、手付金の約2倍の金額を売主側に支払わなければいけません。
非常に高額な金額となってしまいますので、最悪でも解約したい場合は、手付金放棄の期間内までに解約をした方がいいでしょう。
少しのお金でも支払うのが嫌な場合は、前述した売買契約前までには解約しなければいけません。
その④:住宅ローンの審査が通らないから解約
マンションを購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用してマンションを購入するのですが、住宅ローンは誰でも借りることができるというわけではありません。
住宅ローンには審査があるので、審査に通らなければもちろん住宅ローンを利用することはできません。
一般的に売買契約を締結した後に住宅ローンの本審査に入りますので、住宅ローンが通らない場合は、売買契約締結後の解約となってしまいます。
しかし、マンションを購入する際に住宅ローンを利用する場合、住宅ローン特約が付いています。
住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、売買契約締結後に住宅ローンの審査に通らなかった場合、無条件に契約は無効となるもので、手付金なども返金される特約です。
住宅ローンの審査が通らなかった場合、買主の意思ではない解約となりますので、住宅ローン特約が付いていれば住宅ローンが通らなかったとしても特に費用負担することはありません。
クーリングオフの手続きと注意点

最後に、クーリングオフの手続きと注意点について解説してきます。
内容証明郵便による通達を8日以内に行う
まず前提として、クーリングオフをする場合、口頭での伝達や普通郵便で通知をしたとしても、クーリングオフの通知をしたとは認められません。
そのため、きちんと内容が証明される「内容証明郵便」で相手方に通達するということが絶対条件となります。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容を誰が誰に送ったのかといったことを郵便局が証明してくれる郵便方法です。
クーリングオフの説明がされてから、8日以内に通知する必要があるとお伝えしましたが、8日以内に書面で発送の手続きを行えば、8日以降に相手方に届いた場合でも、クーリングオフの効力は認められます。
また、クーリングオフの説明を受けていなかった場合は、8日以内の制限はないので条件さえ整っていれば、いつでもクーリングオフの通知をすることができます。
決済までに通知されると、これもクーリングオフの効力は認められます。
内容証明郵便の書き方
次に、内容証明郵便の書き方について解説します。
内容証明郵便は、郵便局保管分と自らが保管するもの、相手先に通知するものと計3部が必要です。
郵送方法は、手書き方式、パソコンで作成、電子内容証明郵便などの3種類から選択します。
書き方は縦書きの場合、1行を20字以内、1枚26行以内で文書を作成しなければいけません。
横書きの場合は以下のように分類されます。
- 1行20字以内、1枚26行以内
- 1行13字以内、1枚40行以内
- 1行26字以内、1枚20行以内
この範囲内に納めなければいけませんが2枚3枚と複数枚にわたる作成も問題ありません。
電子郵便の場合は、1枚あたり、1,584文字を目安にした方がいいでしょう。
このようなルールを守り、内容証明郵便を作成し郵送することでクーリングオフが利用できます。
まとめ
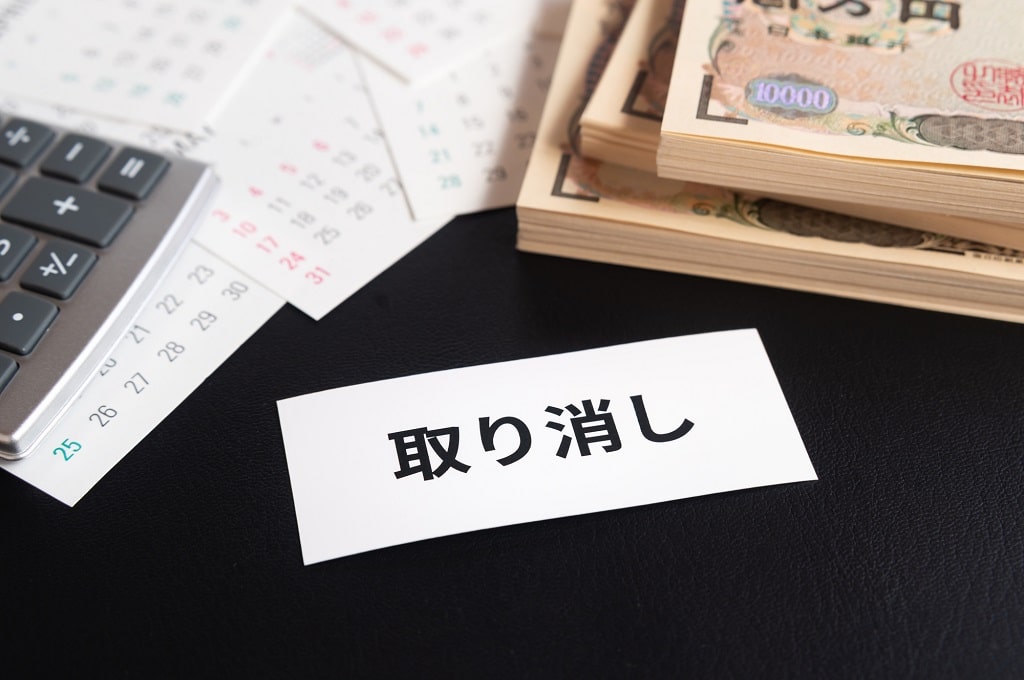
今回は、マンションの購入でもクーリングオフは可能!5つの条件や方法について解説しました。
もう一度おさらいをすると、マンションの購入でもクーリングオフすることは可能です。
ちなみに、クーリングオフするには以下の5つの条件が必要となります。
クーリングオフするための5つの条件
- 引き渡し前であること
- 売主が宅建業者であること
- 買主が宅建業者以外であること
- 制限された場所以外で申し込んでいること
- クーリングオフの説明から8日以内であること
また、クーリングオフ以外でマンションの購入を解約したい場合には、以下の方法があります。
クーリングオフ以外の解約方法
- 売買契約前に解約
- 手付金を支払って解約
- 違約金を支払って解約
- 住宅ローンの審査が通らないから解約
マンションの購入でクーリングオフをする場合、他のクーリングオフよりも少し制限も多く、内容証明郵便などが必要となるのでしっかりと理解しておきましょう。
マンションの購入で失敗しないように、クーリングオフについて本記事を参考にしてみてください。
マンションの売却や買取なら不動産情報サイトMANSION COLLECTのTOPへ戻る
この記事を書いた人
資格:宅建・FP2級・通関士・総合旅行業務取扱管理者
大学生の時に一人旅に目覚め、海外50か国以上を訪れました。その経験を武器に新卒で旅行会社に入社しましたが、入社数年で倒産という憂き目にあってしまいます。悔しさをバネに宅建・通関士・FP資格を無職期間の4年でゲット!現在は不動産会社の窓口勤務ですが、コロナ渦で週休4日ペースが続いているため、新しい資格取得に向けて日々奮闘中です。趣味はペット。特技は英会話。
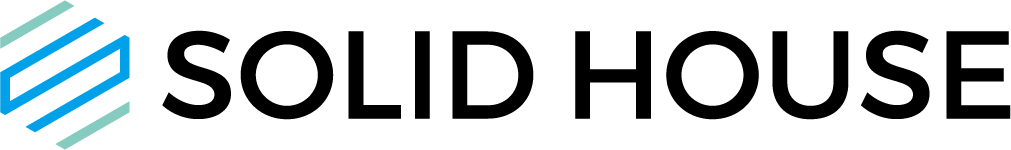
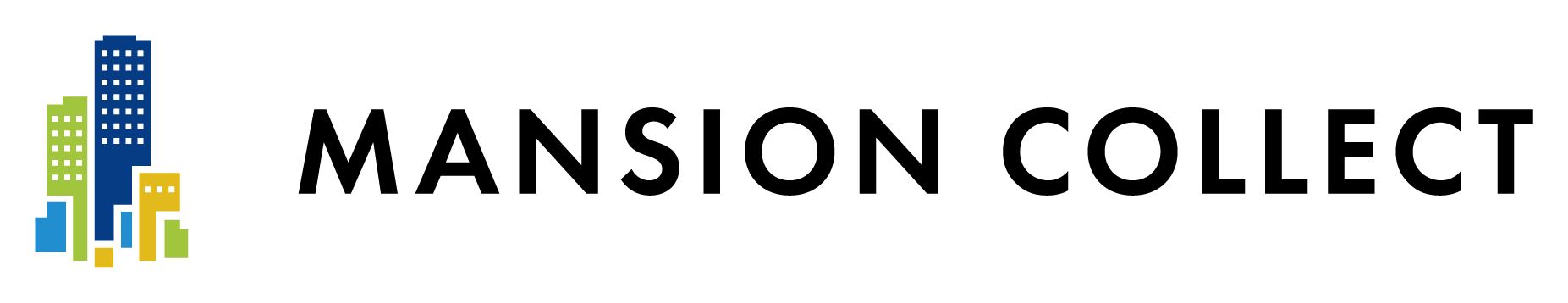
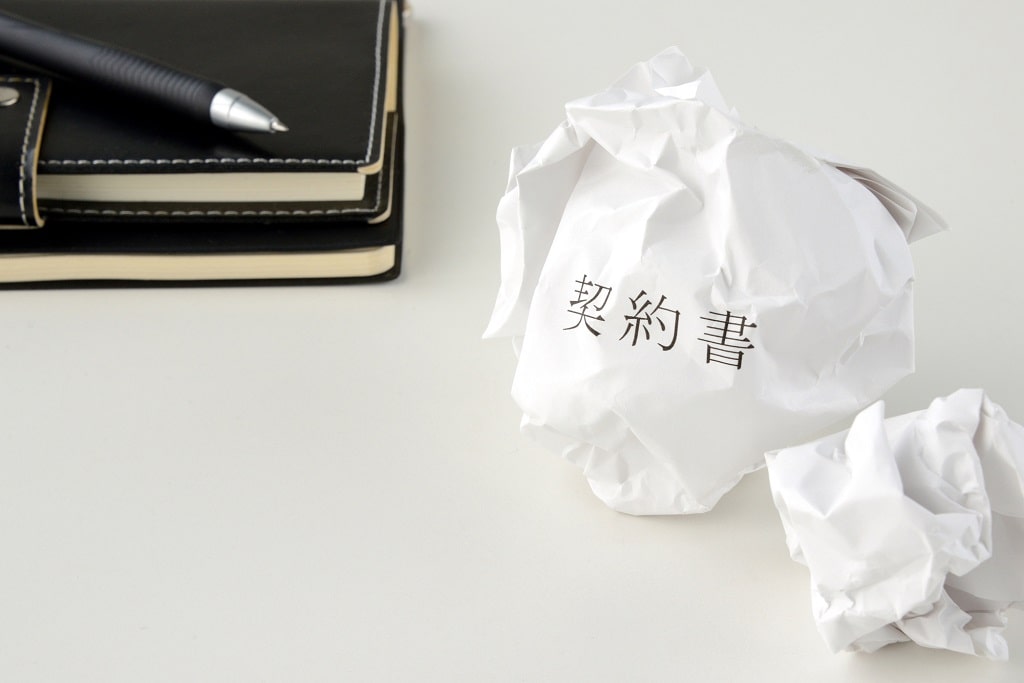
清水みちよ
30代女性