
といった悩みにお答えします。
本記事の内容
- 不動産投資の物件取得前に実施しておきたい計算とは?
- 代表的な2つの利回りと計算方法
- 不動産保有時・売却時それぞれの税金に関する計算方法
- 不動産投資で利回りや税金を計算する際の注意点
不動産投資を成功させるには、事前に念入りにシミュレーションして投資判断することが重要です。
収支の計算ができていないと、キャッシュフローが悪化し投資失敗と言うこともあるでしょう。
特に収支に影響する「利回り」と「税金」の計算は必要不可欠と言えます。
この記事では、利回りと税金の具体的な計算方法から注意点まで分かりやすく解説します。
これから不動産投資を始めるという方は、以下の記事をご覧ください。
-

【初心者向け】不動産投資の始め方!7つのステップで徹底解説!
続きを見る
不動産投資の物件取得前に実施しておきたい計算とは?

不動産投資では、事前に収支を念入りに計算したうえで投資判断することが重要です。
中でも「利回り」と「税金」については、必ず計算しておく必要があります。
利回りの計算
利回りとは、不動産の収益性を占める指標のことです。
利回りを計算することで、次のようなことが把握できます。
- 年間どれくらいの収入を得られる物件なのか
- 何年で資金を回収できるのか
例えば、物件価格1,000万円で利回り10%の物件であれば、年間100万円の収入を得られるということを意味しています。
また、単純に計算して10年で資金を回収できる計算です。
このように利回りは、不動産投資の第一歩ともいえる重要な数値です。
その意味や計算方法をしっかりと理解し、自分で計算できるようになっておく必要があります。
税金の計算
不動産投資では、さまざまな税金が発生します。
税金について理解しておかなければ、思わぬ高額な納税でキャッシュフローが悪化してしまうということもあるでしょう。
不動産投資では、不動産の運用中・売却時にそれぞれ税金が発生するので、どのようなタイミングでどれくらいの税金が発生するのかを正確に把握しておくことが重要です。
それぞれの計算方法については、以下で解説していくので参考にしてみてください。
代表的な2つの利回りと計算方法

まずは、利回りについて見ていきましょう。
利回りには、大きく次の2つの種類があります。
- 表面利回り
- 実質利回り
それぞれ示す内容が異なるため、違いを理解しておかなければ不動産投資で思うように収益を得られない可能性が出てきてしまいます。
不動産投資するうえでは、それぞれの違いと計算方法をしっかりと理解しておくことが重要です。
その①:表面利回り
表面利回りとは、収入と物件価格のみで算出される利益率のことを言います。
表面利回り(%)=年間収入÷物件価格×100
シンプルな計算で算出でき、収益性の目安になるでしょう。
不動産広告で表示される利回りは、一般的には表面利回りです。
表面利回りでは収入を満室時想定の「想定利回り」が示されていることもあります。
ただし、表面利回りは不動産運営で掛かる経費などが考慮されていない点には、注意しなければなりません。
その②:実質利回り
経費までを考慮した利回りが、実質利回りです。
実質利回り(%)=(年間収入-年間経費)÷(物件価格+購入時の諸経費)×100
実質利回りは、より手元に残るお金に近い利回りを算出できます。
不動産投資するうえでは、この実質利回りを計算しておくことが重要です。
例えば、次の条件で表面利回りと実質利回りを見てきましょう。
物件価格:3,000万円(購入時の諸経費は考慮しない)
年間収入:300万円
年間経費:150万円
- 表面利回り=300万円÷3,000万円×100=10%
- 実質利回り=(300万円-150万円)÷3,000万円×100=7.5%
上記のように、表面利回りと実質利回りでは大きな差が生じる可能性があるので注意が必要です。
また、実質利回りで差し引く経費としては、次のような項目があります。
- 固定資産税や都市計画税
- 管理会社への委託料
- 管理費や修繕積立金
- 修繕費
- 保険料
- 税理士や司法書士への報酬
- 保険料
実質利回りを計算することで、より詳細な手元に残るお金を把握することが可能です。
しかし、不動産投資の場合その手元に残ったお金からさらに税金を納める必要があります。
そのため、どれくらいの税金が発生するのかを理解しておかなければ、最終的に手元に残るお金が予想よりも少ないということになりかねないのです。
不動産投資で発生する税金については、以下で確認していきましょう。
不動産保有時・売却時それぞれの税金に関する計算方法
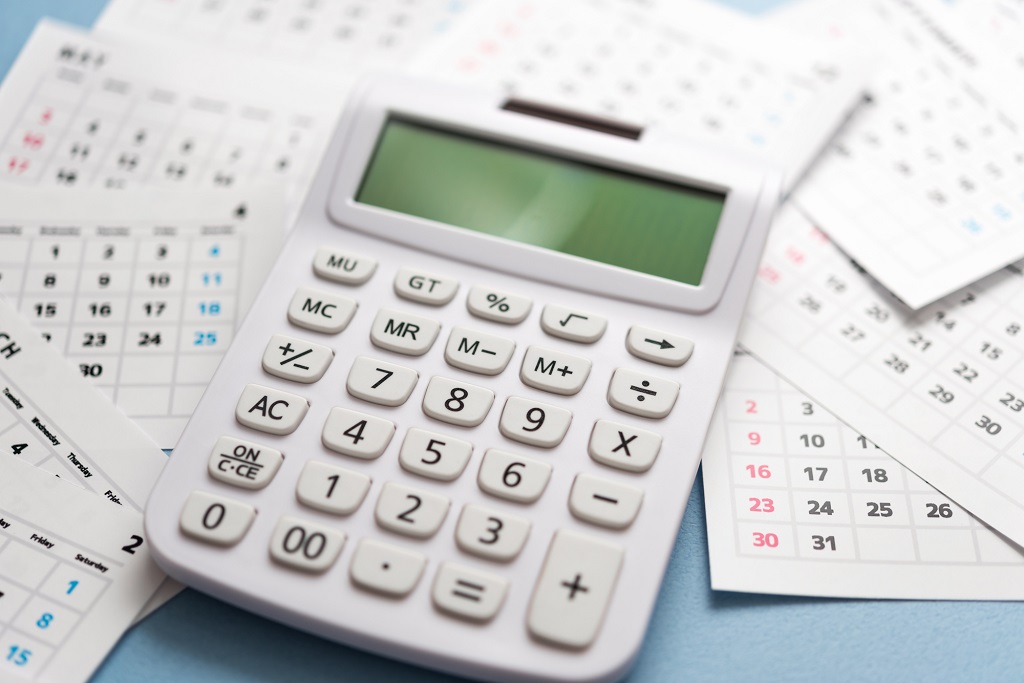
不動産投資では、「不動産を保有しているとき」「不動産を売却するとき」それぞれで以下のような税金が発生します。
- 不動産保有時の収入に対して「所得税」「住民税」
- 不動産売却時の利益に対して「譲渡所得税」
不動産保有時の税金に関する計算方法
不動産運営での収入は、不動産所得と呼ばれ所得税・住民税の課税対象となります。
不動産所得の計算方法は、以下の通りです。
不動産所得=総収入-必要経費
収入には、家賃収入以外にも次のようなものがあります。
更新料
家賃とは別に設定している駐車場代や管理費・共益費
返還の必要のない敷金や礼金・保証料
また、必要経費としては以下の項目があります。
- 固定資産税や都市計画税
- 管理会社への委託料
- 司法書士などへの報酬
- 修繕費
- 管理費や修繕積立金
- 減価償却費
- 交通費などのその他経費
- ローン返済額のうち金利部分
ただし、ローン返済額の元本部分と所得税・住民税は必要経費に含まれないので注意しましょう。
これらの総収入から必要経費を差し引いた額が不動産所得となります。
不動産所得は、他の区分の所得と合算する総合課税の対象なので、不動産所得と給与所得などを合算した額に対して、所得税・住民税の税率が課せられるのです。
所得税
所得税は、所得額に応じで課税率が異なる累進課税制度です。
所得が多くなるほど税率が高くなり、以下の税率が課せられます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
住民税は、所得額に関わらず所得に対して一律10%が課税されます。
仮に、課税所得額が400万円の場合を見てみましょう
- 所得税=400万円×20%-427,500円=372,500円
- 住民税=400万円×10%=40万円
- 所得税+住民税=37.25万円+40万円=77.25万円
不動産所得が大きくなれば、その分給与所得と合算で課税対象額も大きくなるので注意が必要です。
反対に、不動産所得がマイナスの場合は、その分を給与所得と相殺でき課税対象額を抑えられるというメリットもあります。
不動産売却時の税金に関する計算方法
不動産の売却の利益に対して、「譲渡所得税」が課せられます。
譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。
- 課税譲渡所得=売却代金-(所得費+譲渡費用)-特別控除
- 譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
譲渡所得は「売却代金から購入費用と売却費用を差し引いた額」というイメージでよいでしょう。
取得費には、物件の購入額や不動産会社への仲介費用などの購入に掛かった費用が計上されます。
また、譲渡費用としては売却に掛かった経費などが含まれます。
ただし、所得費用は購入したときの価格ではなく、そこから減価償却費を差し引かなければならないので注意しましょう。
また、購入費用が分からない場合は、概算取得費として「売却代金×5%」の計上となります。
物件売却代金からこれらの費用を差し引いた額がプラスの場合に、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は、課税対象の譲渡所得額に譲渡所得税の税率を乗じて算出します。
譲渡所得税の税率は、物件の保有期間に応じて異なり、以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 税率合計 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
例えば、次の条件で見てきましょう。
- 売却額:4,000万円
- 取得費:3,000万円
- 譲渡費用:300万円
- 所有期間:6年
- 課税譲渡所得=4,000万円-(3,000万円+300万円)=700万円
- 譲渡所得税=700万円×20.315%=1,422,050円
上記の場合、700万円の売却益に対して約143万円の譲渡所得税が課せられるのです。
ただし、所有期間の判断基準は売却した年の1月1日と言う点には、注意しましょう。
例えば、2016年5月1日に購入して2021年6月1日に売却した場合、実際の所有期間は5年を超えています。
しかし、2021年1月1日時点では5年を超えていないため、短期譲渡所得の税率が課せられるのです。
上記の場合、短期譲渡所得が課せられると譲渡税は次のようになります。
短期譲渡所得税の場合:700万円×39.63%=2,774,100円
このように、短期譲渡所得では約278万円の税金と倍近くの納税が必要になるのです。
売却する場合は、所有期間に注意して検討するようにしましょう。
不動産投資で利回りや税金を計算する際の注意点

利回りや税金を計算するうえでの注意点としては、次のようなことがあります。
- 利回りが高い物件が良い物件とは限らない
- 将来を想定して計算することが大切
- 数字だけに惑わされないように注意しよう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
注意点①:利回りが高い物件がいい物件とは限らない
不動産広告に掲載されている利回りは、基本的に表面利回りです。
そのため、利回りが高いからといって安易に購入を検討するのはおすすめできません。
表面利回りの場合、経費が含まれておらず、収入も満室を想定している場合もあります。
実際に運営してみると、空室が出てしまう場合や思った以上に経費が掛かり、利回りが低くなってしまう可能性があるのです。
また、利回りが高い物件には高いなりの理由があります。
基本的に利回りが高い物件は、物件価格が安いものです。
- 立地が悪い
- 修繕費用が高額になる可能性がある
- 築年数が古い
このように物件価格を安くしなければ売れない物件と言う可能性があるので、注意しなければなりません。
中には、実質利回りを掲載している不動産広告もあります。
しかし、実質利回りだからと言ってその利回り通りの利益を得られるわけではありません。
実質利回りに含まれている経費の内容や個人の資産状況・借入額によって、実際の利回りは大きく異なります。
掲載されているのが実質利回りでも、含まれる経費の内容を確認し、自分の状況に合わせて計算し直すことが重要です。
このように掲載されている利回りの高さだけで判断するのではなく、実質利回りの計算や実際の物件の情報収集を念入りにしたうえで、投資判断するようにしましょう。
注意点②:将来を想定して計算することが大切
不動産投資では、長期的な視点でシミュレーションすることが重要です。
物件取得時の利回りや税金は、ずっと一定ではなく変化していきます。
特に不動産の場合、経年劣化により修繕費の高騰や家賃を下げなければならない場合も出てくるでしょう。
購入時の利回りがずっと続くと仮定して計画を立てていると、利益が減少した際に大きな損失につながる可能性があります。
また、出口戦略として売却まで含めて考慮しておかなければ、売却時に損失が出てしまい結果として不動産投資の失敗と言う可能性もあるのです。
購入時の利回りや税金だけでなく、リスクなども考慮し将来を想定してシミュレーションするようにしましょう。
注意点③:数字だけに惑わされないように注意しよう
利回りが高い物件は魅力的ですが、数字だけで判断するのは危険です。
先述したように、利回りを高くしなければ売れない物件もあります。
中には、売却前にフリーレントを利用して利回りや入居率を高めている物件もあるのです。
フリーレントとは、一定期間家賃を無料にする入居者との契約のことを言います。
この契約の場合、契約内容によっては無料期間が終わると同時に退去されてしまう可能性があるのです。
入居率が高い物件であっても、レントロールなどを確認して契約方法を把握するなど、できるかぎり情報を集めておく必要があります。
不動産投資するうえでは、数字だけでなくできるだけ詳細な情報を収集して判断することが重要です。
まとめ

不動産投資する前に必要な計算についてお伝えしました。
不動産の購入前には、「利回り」と「税金」についてしっかり計算してシミュレーションしておくことが重要です。
計算があいまいでは思うように利益が上がらないだけでなく、大きな損失につながり不動産投資が失敗してしまう可能性もあります。
それぞれの意味や計算方法を把握して計算することで、物件の購入の大きな判断材料とできるでしょう。
この記事を参考に、不動産投資で必要な計算方法を理解し、不動産投資を検討するようにしましょう。
マンションの売却や買取なら不動産情報サイトMANSION COLLECTのTOPへ戻る
この記事を書いた人
資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)
地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。
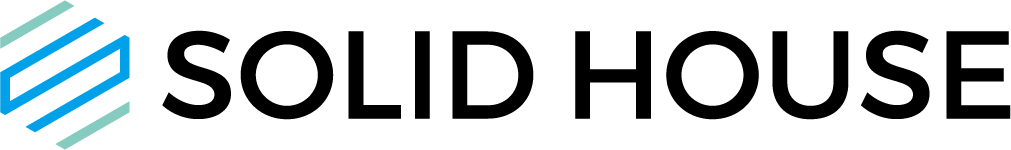
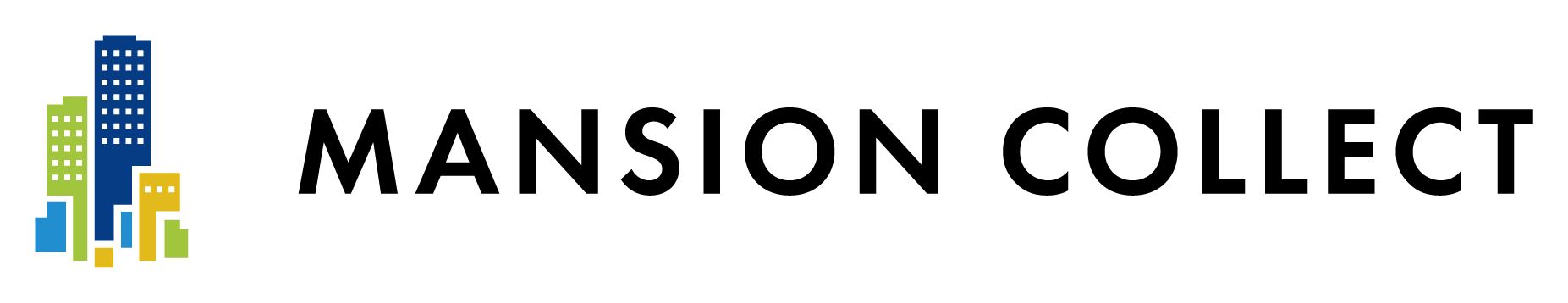

逆瀬川勇造
30代男性