
といった悩みにお答えします。
本記事の内容
- サラリーマンの不動産投資でも確定申告が必要?
- 家賃収入は不動産所得として計上
- 青色申告とは?
- 確定申告の流れ
「不動産投資しているけど確定申告って必要だろうか?」「青色申告ってよく聞くけど何が良いの?」そのような疑問をお持ちのからもいらっしゃるでしょう。
サラリーマンの副業としても人気の不動産投資。
不動産投資で収入がある場合、確定申告が必要なのか分からずに迷っている方も多いでしょう。
不動産投資で、一定の金額以上の収入がある場合は、確定申告が必要です。
また、損失が出た場合でも確定申告することでお得になる場合があります。
しかし、サラリーマンの場合は確定申告になじみのない方も多く、申告方法など分からないことも多いでしょう。
この記事では、不動産投資での確定申告の必要性や、申告の流れについて分かりやすく解説します。
併せて、青色申告のメリット・デメリットにつても紹介するので、参考にしてください。
これから不動産投資を始めるという方は、以下の記事をご覧ください。
-

【初心者向け】不動産投資の始め方!7つのステップで徹底解説!
続きを見る
サラリーマンの不動産投資でも確定申告が必要?
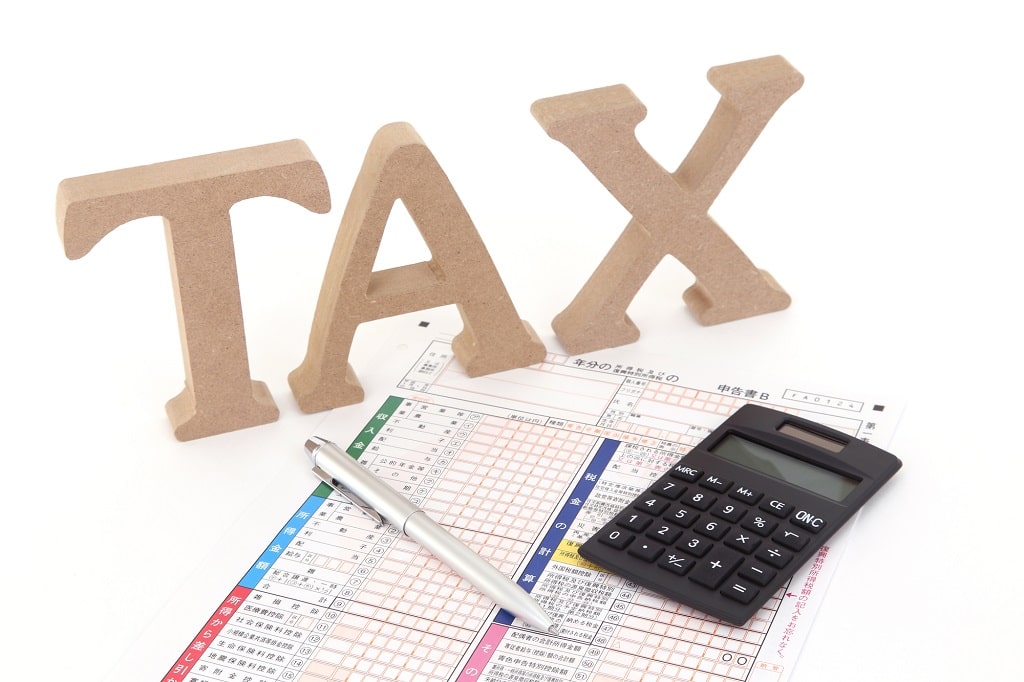
不動産投資での収入額が一定以上になると、確定申告が必要です。
そもそも、確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの収入の合計から所得税を計算し、申告・納税する手続きのことを言います。
サラリーマンなど会社から給与をもらう場合、毎月の給与からあらかじめ見込み額で所得税が天引きされています。
ただし、この天引き額には、給与の変化や控除などは考慮されていません。
そのため、年末に所得が確定し所得税が決まると引きの額と実際の所得税が異なることがあるのです。
その誤差を修正し、追加の納付や払いすぎた分の還付を受けるのが年末調整となります。
会社の給与のみの所得しかない場合、確定申告は必要がありません。
しかし、副業などで別に所得が発生する場合は、自分で確定申告しなければならないのです。
年間20万円を超える所得を得たら確定申告しなければならない
給与以外の所得が発生する場合、すべての場合で確定申告が必要なわけではありません。
確定申告が必要な条件には、次のようなものがあります。
確定申告が必要な条件
- 会社からの所得が2,000万円を超える場合
- 副業として年間20万円以上の所得がある場合
- 2か所以上から給与をもらっている人
- 医療費控除や住宅ローン控除を受ける人
そのため、不動産投資での収益が年間20万円以上になる場合は確定申告が必要になるのです。
ただし、住民税は20万円以下なら申告不要といった制度はありません。
副業で収入が1円でも発生する場合は、住民税の申告は別途必要になるので忘れずに申告するようにしましょう。
損失が出た場合も確定申告したほうがよい
不動産投資の場合、収益が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
しかし、これは確定申告する必要がないというだけで、してはいけないというわけではありません。
不動産投資では、赤字の場合に確定申告することで税制上お得な措置を受けられる可能性があるのです。
不動産投資での赤字を確定申告することで、次のような制税上の優遇措置を受けられます。
- 損益通算
- 繰越控除
損益通算とは、赤字の所得を給与所得などの他の黒字の所得と相殺して申告できる制度です。
例えば、不動産所得で200万円の損失があり、給与所得で500万円の所得がある場合、相殺した300万円で確定申告できます。
この場合、本来500万円に対して課税される所得税が、300万円で課税されるので、払いすぎた所得税の還付と住民税の減額を見込めるのです。
また、その年だけで相殺しきれなかった赤字は翌年以降最大3年間繰越せるのが、繰越控除です。
例えば、1年目に損益通算しても500万円の赤字が出た場合、翌年の所得からもこの500万円を差し引けます。
さらに、控除しきれない場合は翌々年にと、3年間持ち越すことが可能です。
損益通算と繰越控除により、所得税の還付と住民税の減額が受けられる可能性があり、所得が大きければそれだけ節税効果が見込めるでしょう。
ただし、適用するには確定申告が必要となるため、赤字の場合でも確定申告することが大切なのです。
確定申告を税理士に依頼することも可能
確定申告は、不動産所得の計算や申告書の作成など、手間や時間が掛かるものです。
また、計算も複雑になり、ミスがあると修正などでさらに時間が掛かってしまいます。
確定申告は、翌年2月16日から3月15日までと期間も決まっているため、仕事の都合などで確定申告の時間が取れないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、税理士に確定申告を依頼することも可能です。
税理士なら、申告書の作成から確定申告までを担ってくれるので、手間や負担を掛けずに済むでしょう。
ただし、税理士への依頼料として10万円程掛かるので、自分でどこまでできるのかを考慮して検討することが大切です。
また、確定申告時期は税理士への依頼が立て込んで断られる場合もあるので、早めに依頼するようにしましょう。
申告時期には、無料で相談会などを実施している場合もあるので、利用するのもお勧めです。
家賃収入は不動産所得として計上

不動産投資では、不動産を貸し付けたることによる家賃収入が収益です。
この家賃収入での所得は、所得区分のなかで「不動産所得」に分類されます。
不動産所得の計算式
不動産所得は、受け取った家賃収入がそのまま所得となるわけではありません。
家賃収入から経費を差し引いた額が、不動産所得となり、所得税が課税さるのです。
不動産所得=不動産収入-必要経費
そのため、家賃収入が年間20万円以上ある場合でも、経費を差し引いたら20万円以下になる場合、確定申告は必要ないのです。
不動産所得の収入には、次のようなものがあります。
- 家賃収入
- 駐車場収入(家賃とは別に設定している場合)
- 管理費や共益費
- 礼金や保証金などで返却の必要のない費用
- 更新料
不動産投資で認められる経費
不動産所得では、収入から必要経費を差し引けます。
ただし、すべての経費を差し引けるわけではないので、注意が必要です。
必要経費として認められるものには、次のようなものがあります。
- 管理会社への委託費用
- 修繕費
- ローンの金利
- ローンを受けた年の手数料
- 広告費
- 仲介手数料
- 不動産取得税や固定資産税・都市計画税
- 損害保険料や火災保険料
- 司法書士や税理士への報酬
- 減価償却費
また、不動産や税金などの勉強のための書籍や不動産屋への手土産、物件視察のための交通費なども経費計上できます。
ただし、あくまで常識の範囲内での項目・金額が経費として認められるものです。
交際費などの頻度や金額が多いといった場合では、税務署からチェックを受ける可能性があるので注意しましょう。
不動産投資で認められない経費
次のような支出は必要経費として認められないので、注意が必要です。
- 所得税や住民税
- 配偶者や親族への給与(青色事業専従者給与を除く)
- ローン返済のうち元本部分
- 個人事業主のスポーツジムの入会金などの福利厚生費
- 駐車違反などの反則金や罰金
ただし、経費として認められるか認められないかは条件によっても異なる場合があります。
例えば、修繕費であっても物件の資産価値を上げるための修繕費用は一括での計上が認められず、減価償却として計上しなければなりません。
それに対し、原状回復のための修繕費は一括での経費計上が可能です。
経費として認められるか認められないかは判断が難しい場合があるので、迷う場合は税理士に確認することをおすすめします。
青色申告とは?

確定申告を進めていると青色申告・白色申告という言葉を耳にする機会があるでしょう。
青色申告とは、一定の帳簿を揃えたうえで、その記録を元に確定申告する制度のことを言います。
青色申告することで、税制上のお得な措置を受けられるのです。
青色申告するには、次に条件を満たす必要があります。
- 開業届を提出している
- 青色申告承認申請書を税務署に提出している
- 正規の簿記の原則に従って作成した帳簿を備え付けている(複式簿記か簡易簿記)
ちなみに、青色申告でない確定申告方法を白色申告と言います。
青色申告のメリット
青色申告することで、税制上の優遇措置を受けられるというメリットがあります。
具体的には、次のような優遇を受けられます。
- 青色申告特別控除として最高65万円までを控除できる
- 青色事業者専従者給与を必要経費に計上できる
- 30万円未満なら一括で経費計上可能
青色申告特別控除として最高65万円までを控除できる
青色申告の大きなメリットが、最高65万円を控除できることです。
複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書を貼付し、e-Taxで確定申告することで、65万円を所得から控除できます。
e-Taxで確定申告しない場合は55万円、単式簿記での記帳の場合は10万円の控除となるので注意が必要です。
青色事業者専従者給与を必要経費に計上できる
配偶者や親族などへの給与支払いは、通常では経費として認められません。
しかし、青色申告者の場合、事前に届け出をすることで家族への給与の支払いを経費として計上できるようになるのです。
ただし、不動産所得では、不動産賃貸業が事業規模でなければ青色事業専従者給与が経費に計上できない可能性があるので注意しましょう。
30万円未満なら一括で経費計上可能
白色申告の場合、取得価格が10万円をこえる固定資産の場合、減価償却資産として数年に分けて経費計上しなければなりません。
青色申告している場合、取得額が30万円未満のものであれば、その年に一括で経費計上可能になります。
そのため、利益が出そうな年は、この制度を利用して経費計上することで所得を抑えることが可能です。
ただし、合計上限が300万円までとなります。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットとしては、次のようなことがあります。
- 事前に届け出が必要
- 記帳が難しい
事前に届け出が必要
青色申告するには、事前に税務署への届出が必要です。
一度、届出してしまえば、翌年以降は届出の必要がなく、取りやめの申請を出すまでは青色申告となります。
記帳が難しい
青色申告は、基本的に複式簿記での記帳が必要です。
簿記の知識が少ない人には、記帳を負担に感じる方もいるでしょう。
ただし、白色申告する場合でも帳簿は必要なので、確定申告する以上は簿記の知識は必要になります。
記帳などが難しい場合は税理士に依頼することも可能です。
また、確定申告ソフトを利用すれば、知識がなくても記帳できるので、利用しながら簿記の知識を身に着けることをおすすめします。
確定申告の流れ

ここでは、確定申告の流れについて解説していきます。
確定申告の大まかな流れは、次のとおりです。
- 帳簿をつける
- 必要書類を揃える
- 申告書を作成する
- 税務署に提出する
- 税金を納付する
それぞれ見ていきましょう。
手順①:帳簿をつける
日々の取引は帳簿に記録していきます。
会計ソフトなどを利用すれば、初心者でも簡単に帳簿付けができます。
無料のソフトなども多くあるので、利用するとよいでしょう。
手順②:必要書類を揃える
不動産投資の確定申告の場合、次のような書類が必要になります。
- 確定申告書
- 身分証明書やマイナンバーカード
- 家賃収入などの不動産関連書類(賃貸借契約書や家賃明細書)
- 経費や控除関連書類(固定試案税納付書やローン返済表・管理費などの支払いが分かる書類)
- 源泉徴収票
手順③:申告書を作成する
確定申告書を作成します。
e-Taxを利用すれば、パソコン上で確定申告書の作成から提出まで可能です。
青色申告で65万円の控除を受けるためには、e-Taxでの申告が必要になります。
手順④:税務署に提出する
確定申告期間内に、税務署に確定申告します。
確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
申告方法には、次の3つの方法があります。
- 窓口に持参する
- 郵送する
- e-Tax
税務署の窓口へ持参すれば、最低限のチェックを受けられるので、不安がある人は窓口で申請するとよいでしょう。
ただし、確定申告時期の窓口は混雑し、また申請できる時間も決められています。
忙しいなどで申請に行けない場合は、郵送での申請も可能です。
郵送の場合は、必要書類を揃えて送付するので時間がなくても利用できます。
郵送の場合は、消印日が申請日になるのでギリギリでの申請の場合は、期限を超えないように注意しましょう。
e-Taxでの申請なら、確定申告書の作成から申請までをインターネット上でできるので、簡単に申請できます。
マイナンバーカードやカードリーダーなどの準備が必要ですが、一度登録すれば翌年以降はスムーズに申告できるでしょう。
確定申告期間内に申告しない場合、延滞税や無申告加算税が課せられてしまいます。
申告期限から日数が過ぎれば、それだけペナルティも大きくなるので、申告を忘れていた場合は、すぐに対応するようにしましょう。
手順⑤:税金を納付する
確定申告してお終いではないので、注意しましょう。
確定申告後に税金の納付が必要です。
納付方法には、その場での現金納付と振替納税の2つの方法があります。
現金納付の場合は、3月15日まで、振替納税の場合は4月下旬ごろの引き落としです。
期限内に一括での納税が難しい場合、申請することで分割納税や納税までの猶予を貰うことが可能です。
ただし、一定の条件を満たす必要があるので、まずは税務署に相談するとよいでしょう。
まとめ

不動産投資での確定申告の必要性や青色申告のメリット・デメリット、確定申告の流れをお伝えしました。
サラリーマンの不動産投資であっても、収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
しかし、20万以下の場合でも確定申告することで、税制上の優遇措置を受けられる可能性もあります。
確定申告に慣れないうちは、記帳や申告書の作成など難しく感じるかもしれませんが、不動産投資を続けていくうえでは確定申告や記帳は必要な知識でもあります。
確定申告に不安がある場合は、税理士に依頼や相談しながら進めることも可能です。
この記事を参考に、確定申告について理解し、正しい知識を身に着けて自分でも申告できるようにしましょう。
これから不動産投資を始めるという方は、以下の記事をご覧ください。
-

【初心者向け】不動産投資の始め方!7つのステップで徹底解説!
続きを見る
マンションの売却や買取なら不動産情報サイトMANSION COLLECTのTOPへ戻る
この記事を書いた人
資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)
地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。
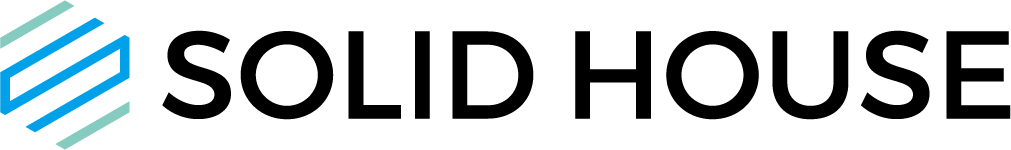
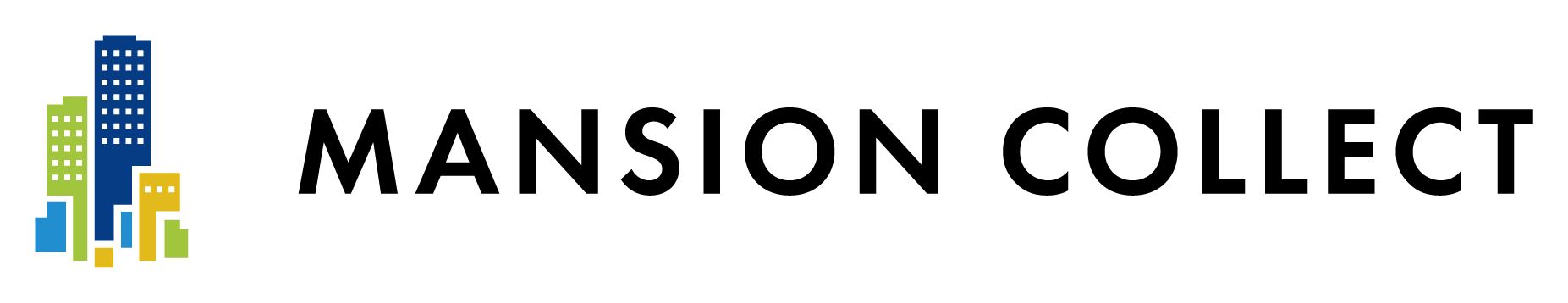

逆瀬川勇造
30代男性